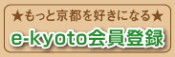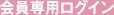|
流しびなは平安時代に始まったとされる、子どもの健やかな成長を願って小さな人形を子どもの身代わりに川や海に流し厄を払う行事で、ひな祭りの原型とされています。 下鴨神社では、公募で選ばれ結婚を控えた男女が、十二単に衣冠装束姿に身を包み、桟俵(さんだわら)に乗せ た和紙人形を境内の御手洗川に流します。また、十二単・束帯衣着付けの披露や、お内裏さまと記念撮影などの行事が行われ、毎年多くの人が 集まります。 詳細はこちら
|
京のおひなまつり

桃の節句は江戸時代に定められた 五節句(七草粥・桃の節句・端午の節句・七夕祭・菊の節句)のうちの一つで、
女の子の成長と幸せを願ってひな人形を飾り、お祝いをします。
別名「上巳(じょうし)の節句」とも呼ばれ、悪日とされていた日に紙で人形を作り、
けがれを払ってから川に流すという「流し雛」の風習と平安時代の
「御人形(ひいな)遊び」とが結びついて、江戸時代に現在のようなひな祭になったといわれています。
ひな祭りの日には、こんなおばんざいを食べます。→「京のおばんざいレシピ・おひなさんに備えて」
「生まれた子供が健康で優しい女性に無事に育ってくれますように」 といった家族の温かい思いが込められているのです。
下鴨神社の流しびな
宝鏡寺のひな祭り
上賀茂神社の桃花神事
 |
桃花神事(とうかしんじ)とは五節句の重要な行事の一つで、神前に桃の花や辛夷 (こぶし)の花、よもぎ餅などの神饌(しんせん)をそなえ、無病息災を祈ります。 儀式は本殿側の川の前で参拝することに始まり、宮司たちの行列が古来の方法にのっとって神前に神饌をそなえます。 祭典後は、境内のならの小川にて雛流しが執り行われ、この行事には一般の観光客も参列することが出来るので、儀式を間近で見ることができます。おごそかにとりおこなわれる神事は、今も昔も変わりません。
|
市比賣神社のひいなまつり
 |
市比賣神社で行われる「ひいなまつり」は、他とは少し変わった雛まつりです。 本来の神事も行われますが、面白いのが衣紋(衣冠・十二単)の着付け方法の紹介や、人が扮する人雛、五人囃子の雅楽、それにあわせた三人官女の舞、人形に災厄を移す「天児(あまがつ)ノ儀」など、女性が1年の厄払いをするひな祭りの起源と雅やかな公家社会が再現されるところです。 また、希望者は服の上から小袿(こうちぎ)を羽織らせてもらい、ひな壇に登っての記念撮影ができます。また、運が良ければ投扇興(扇を投げて台にのった的を落とす遊び)や、双六などのいにしえの遊びを体験することができます。 スタッフレポートはこちら!
|
その他のひな祭り
| ■杉本家・特別一般公開「ひな飾り展」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉本家に伝承されてきた人形や、9代目夫人の生家から寄贈された享保雛、古今雛、男子・女子の市松人形、有職雛と右近左近の両大臣、また桜と橘などのお雛飾りが展示されます。 期間中の予約は不要ですが、事前に公式ホームページに記載の拝観の際の注意を読んでおきましょう。 ※工事期間中につき見学できない部屋があります。 2023年から邸内に新設された茶房にて、杉本家ゆかりのお茶やオリジナルで製作した甘酒などが楽しめます。
■「千本ゑんま堂 引接寺」...御殿雛とつるし飾りが旧暦の雛祭りまで公開され、薄茶席も設けられます。(※過去の例) ■「亀山城下ひなまつり」...江戸時代や明治・大正時代の歴史あるおひなさまが各地の店舗や町家に飾って公開しています。(※過去の例) ■「みんなのひな祭り in 綾部」...東光院境内のあちこちに、檀家から提供された約300体の人形。 中には10段越えのひな壇もあります。 ■「加茂船屋雛まつり」...JR加茂駅の西側に位置する船屋通りとその周辺の約50軒で雛人形が展示されるほか、空地や広場を利用したマルシェ等のイベントも予定されています。 (※過去の例)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京の豆知識
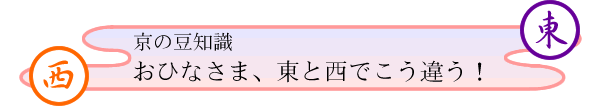
◇男雛と女雛は左右どちらが正しい?◇
「お内裏様」「お雛様」という呼び方は、男雛と女雛の両方を指します。
現在、お内裏様の並べ方は、関東では向かって左が男雛(親王)、右が女雛(内親王)。
関西では反対となっているそうです。古来日本では左が上位(左大臣は右大臣より偉い)。
ただこの左右は一番偉い人が下位の者を見た場合の左右なので、
雛飾りでいえば男雛から見た左右。
そのため、御内裏様、御雛様を見上げる立場からすると向かって右が上位と言うことで
男雛が向かって右、女雛が左にある(別に男尊女卑論では有りません)関西の方式が日本の古来からの方式といえそうです。
これに対して関東方式は、明治以降ヨーロッパ等の習慣にあわせて女性を向かって
右に配する方式を日本の皇室が採用した(西洋式の行事について)ことから、
東京の人形商協会が向かって右を女性、左を男性の配置を正式すると決定したためだそうです。
◇おひな様のお道具◇
関東の雛飾りと関西の雛飾り、よく見ると何かが違います。
そう、それはおひな様のお道具です。
京都の雛飾りには、たんす、長持ち、などの一般的なお道具の他に、
調理器具や食器、おくどさん(釜)などの生活用品がありますが、
関東の雛飾りには一般的にはありません。
これも京都ならではの風習なのでしょうか。
主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。



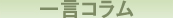
 2024年の祇園祭でも新たな話題がありました。
かつて「犬神人(いぬじにん)」や「弦召(つるめそ)」と呼ばれる人々が住んでい...
2024年の祇園祭でも新たな話題がありました。
かつて「犬神人(いぬじにん)」や「弦召(つるめそ)」と呼ばれる人々が住んでい...