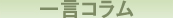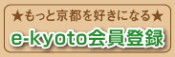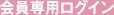2024年の祇園祭でも新たな話題がありました。
かつて「犬神人(いぬじにん)」や「弦召(つるめそ)」と呼ばれる人々が住んでい...[続きを読む]
2024年の祇園祭でも新たな話題がありました。
かつて「犬神人(いぬじにん)」や「弦召(つるめそ)」と呼ばれる人々が住んでい...[続きを読む]2024年9月8日(日)の行事一覧
※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。
御田刈祭・相撲神事

収穫に感謝する神事が行われた後、神相撲の奉納が行われます。
氏子代表の力士がお祓いを受け、清めの紙と呼ばれる半紙をくわえ、
四本柱を塩で清めて相撲を取ります。
江戸時代の中頃から続いているという興味深い行事です。
小中学生による子供相撲も行われ、
たのもしい取り組みに周囲の声援が飛び交い、にぎやか。
| ■場 所: | 大原野神社 |
| ■期 間: | 2024年9月8日(日) |
| ■時 間: | 12:00~ |
| ■アクセス: | JR「向日町」駅より 阪急バス「南春日町」 |
| ■お問合せ: | 075-331-0014 |
| ■詳細ページ: | 大原野神社公式ホームページ |
金剛定期能

お馴染みの例会です。今回は復曲公演です。
演目::能「定家」、狂言「鬼の継子」、仕舞
| ■場 所: | 金剛能楽堂(京都市上京区烏丸通一条下る龍前町590) |
| ■期 間: | 2024年9月8日(日) |
| ■時 間: | 13時~ |
| ■料 金: | 6000円(一般)、3000円(学生) |
| ■アクセス: | 地下鉄烏丸線「今出川」駅 |
| ■お問合せ: | 075-441-7222 |
| ■詳細ページ: | 金剛能楽堂公式ホームページ |
季節の光景...萩

萩を詠んだ歌が万葉集で好まれていたように、京都で紅白の萩を見られる所はたくさんあります。お彼岸さんには、お重につめた萩餅を持って萩探訪などとしゃれこんでみては?迎稱寺を囲む土塀に沿って萩が咲いています。崩れそうにわびた土塀と萩との組み合わせは、古都ならではの良き景色です。
「萩の寺」常林寺は人の半身がすっかり隠れてしまう程の勢いのある萩が生い茂っています。
明治維新で活躍した三条実萬、実美親子ゆかりの梨木神社には、「染井の名水」で育った紅白の萩が見られ、当神社萩の会の元会長であった湯川秀樹が萩を詠んだ歌碑があります。
| ■詳細ページ: | 梨木神社公式ホームページ 京都の萩まつり特集 梨木神社周辺情報 |